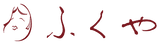うつぼ草こゝ五月雨の湊かな
鈴木道彦
夏至(げし)は、6月22日頃、および小暑までの期間を指します。
夏至は、一年で一番昼の時間が長い日です。また、太陽の位置が最も高くなり、影が短くなる日でもあります。しかし、実際は梅雨の時期の最中であり太陽が見れない日があると思います。
旧暦では6月末と12月末に祓(はらえ)の行事が行われていました。かつては夏も疫病がはやりやすい時期であったためです。「和やか(なごやか)」という意味の「和し(なごし)」に、夏が越せますようにと願いを込めて「夏越しの祓(なごしのはらえ)」という行事が行われています。現代でも川に形代(かたしろ)を流したり、神社などで茅の輪(ちのわ)をくぐったりと身を清める禊が受け継がれています。
その際に「水無月」と呼ばれる和菓子を食べることでも半年間の穢れを払うとされていました。魔除けの効果や暑気払いの意味も込められています。