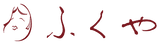一雫こぼして延びる木の芽かな
有井諸九
雨水(うすい)は、2月19日頃、および啓蟄までの期間を指します。
少しずつ雪が雨に変わり、氷が水に解ける様子を表しているとされます。大地が目覚め潤い始めると水蒸気が立ちのぼり霞がたなびき始めます。立春から2週間程度が経ちゆっくりと暖かくなることを目で知ることができます。ですが、実際にはまだ寒い日が続きます。
地面に積もっていた雪などが解けることで、草木の芽吹きを確認することで昔は農業の準備を始める目安の時期とされていました。
日本にはかつて、人形(ひとがた)に穢れを移して水に流すという風習がありました。これが現在の鳥取県の一部でも行われている「流し雛」の原型とも言われ、中国から来た上巳の節句と結びつき、次第に3月3日に行われている「ひな祭り」へと発展したとされています。雨水の日にひな人形を飾ると「良縁に恵まれる」という説もあるようです。