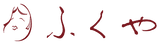春立つや誰も人より先へ起き
上島鬼貫
立春(りっしゅん)は、2月4日頃、および雨水までの期間を指します。
二十四節気の1番目の季節となります。春が立つという名前の通り、春の始まりを表しており、「八十八夜」など様々な行事の基準日ともなっています。
また、立春の前日は2月3日の節分です。節分には「季節を分ける」という意味があり、本来は「立春」「立夏」「立秋」「立冬」それぞれの前日である年4回に設けられていました。しかし、二十四節気の1番目である「立春」の前日は、年の分かれ目に等しい意味を持つとして、今日まで2月3日の節分が年行事として取り組まれています。
正月など何か新しいことを始めるときや人生の節目などに、縁起物を食べるとされています。「立春」も同じく季節の始まりであるので、縁起物を食べるとよいとされており、立春の朝に作ってその日のうちに食べる和菓子を「立春生菓子」と呼びます。
また、あずき餡や餅には邪気を払う力があるとされています。中でも立春に食べる大福は「立春大福」と呼び、福の文字が入ることから特に縁起がよいとされています。「うぐいす餅」や「桜餅」なども春を感じることができる和菓子として昔から食されています。