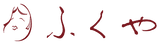春待つや空美しき国に来て
佐藤紅緑
大寒(だいかん)は、1月20日頃、および立春までの期間を指します。
二十四節気の中でも最も寒さが厳しい時期とされ、1月20日を二十日(はつか)正月、別名で骨正月とも呼びます。名称の由来は、正月に鰤が欠かせない京阪神地方で、正月に使った鰤をこの日に骨や頭まで食べ尽くすことから。
正月に関する行事の祝い納めの日とされ、飾り物やお供え物は全て片付けることといわれております。正月に迎えた神様がそれぞれの場所に戻る日とも言われており、19日の夜に小豆ごはんや尾頭付きの魚などをお供えする地方もあります。
キク科フキ属の多年草であるフキから、早春になって花茎が伸びてきたものが蕗の薹(ふきのとう)で、花の蕾の状態のものです。全国各地で見られる日本原産の植物で、雪解けを待たずに顔を出すことから「春の使者」とも呼ばれています。
蕗の薹は食用にもなり、ほろ苦さと香りを好む人も多いことでしょう。天ぷらにするほか、炒め物や煮浸し、みそ汁の具材にしても美味しくいただけます。そのほか、煎じて飲むと咳止めの効果や、解熱作用もあるので風邪の初期症状には薬用としても重宝します。