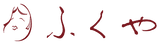大はらや蝶の出でてまふ朧月
内藤上草
啓蟄(けいちつ)は、3月6日頃、および春分までの期間を指します。
「啓」はひらく・解放という意味を持ち、「蟄」は隠れた虫を意味します。昔は、かえるなどの小さな生き物も含めて虫と呼んでいました。つまり、冬ごもりしていた小さな生き物たちが春の気配を感じ、はいでてくる様子を表しています。
ゼンマイや独活(うど)などの様々な山菜が顔をそろえる時期でもあります。中でも蕨(わらび)は古くから食用とされており、蕨の早春の若芽は「早蕨(さわらび)」と呼ばれ万葉集にも収載されています。根からとれるでんぷんでわらび餅が作れ、幅広い世代に人気がありますよね。
釈迦が悟りの境地に達して亡くなったことを涅槃と呼び、各寺院でその様子を描いた涅槃図を掲げお経を読む涅槃会が現在の多くは3月15日に行われます。その際に釈迦の遺骨である仏舎利(ぶっしゃり)を模して作られる涅槃団子を食べて無病息災を祈る風習もあります。